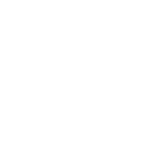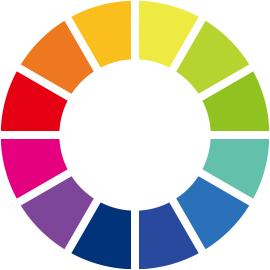映画「カメラを止めるな!」の製作元ENBUゼミナールとは?【後編】

「ENBUゼミナール」では、1年間のレギュレーションとは別にワークショップと呼ばれる授業が行われている。『カメラを止めるな!』もシネマプロジェクトなる長期的なワークショップから生まれた作品の一つで、上田慎一郎氏をワークショップの監督として迎え、オーディションで選ばれた12人の役者たちが演じた。映画祭での受賞から火がつき、2018年を代表するタイトルといえる“カメ止め”を、スクールの代表とOG2人はいかに捉えているのか。今回の後編ではそれぞれの視点でこの映画を語ってもらい(未見の方は注意!!)、さらにはインディペンデントな小規模作品の可能性を聞いた。
Photo_Daiki Sekimizu(TRYOUT)|Edit&Text_Yoshio Horikawa(TRYOUT)
違和感を含んだ伏線がスリリングに回収され、最後のメイキング映像で思わず涙腺が緩む。
――『カメラを止めるな!』は数百万円で製作されたと聞いたのですが、邦画のヒット作品というとどれくらいの費用が相場なのでしょうか?
早川千絵 聞くところによるとプロが撮るけど、いわゆる低予算と呼ばれるような映画が3,000万円から5,000万円くらいだと。
市橋浩治 有名な俳優がたくさん出ていたり、テレビで番宣していたりするような作品は5億くらいとかの話だと思いますけど、いま邦画で多いのは5,000万円、少なくて3,000万円以下でしょうかね。
――そう考えると、『カメラを止めるな!』は異例ということですね。
早川 本当に。異例中の異例ですよね。
――お三方も観られたと思うのですが、どのような感想をお持ちでしょうか?
藤原佳奈 演劇を観た時の体験と近いものがあると感じていて、なんかこう“共犯関係”というか。映画って自分とは全く関係のない時間軸で撮られたものを覗き見している、ちょっと俯瞰して観るという関係性だと思っているんですけど、『カメラを止めるな!』の場合は、同じ時間軸を観客同士で共有しているような気がしました。1回しか観てないですけど、演劇体験と似ているなって。観客席に座っている人みんなで一緒に見守っているような。生の体験というか。


市橋 わかる、わかる。みんなで観ているという映画館の空間込みの楽しさ、みたいなところはあるよね。あと上田監督が意図していたというか、さじ加減で悩んでいたんだけど。37分間ワンカットの間に違和感だけがずっとあるわけですよ、それもはっきりとした。「え、これ面白いの!?」っていう。
――わかります(笑)。まさか最後までこの調子なんだろうかって。
市橋 そう、まずはこのまま続くのかという変なストレスがあって、話が1ヶ月前に戻って多少の謎解きが始まって、「あぁそういうことか」みたいな。それで最後の第3部のところで、その伏線を強烈に回収していくわけですが、それが痛快なんですよ。なので思わず笑っちゃう。藤原さんの言うように一体感を伴って。
藤原 伏線を回収するコメディだと三谷幸喜さんとかいろんな方が作っていらっしゃると思うんですけど、全部を上手くまとめ上げるというよりも、何が起こるかわからない感覚。そのよくわからない不安が、徐々に解決されていくというスリルが良かったです。
市橋 あとはワークショップだからこそできたのかなと思います。ワークショップにリハーサルと、付き合っている時間が長いなかで当て書きをしたんですよ。一人ひとりの役者の性格をちゃんと見極めたうえで、その人に合ったキャラクターにシナリオを書き換えていく。演者の素の部分も含めて人柄を極端にしちゃう。例えばお腹をこわす山越俊助役を演じた山﨑俊太郎。彼はうちの卒業生なんですが、普段から挙動不審な感じなんですよ(笑)。もちろんちゃんとしているんだけど、それが上手く出せなかったりするキャラクターで、それが見事にハマっているなと感じました。ワークショップでずっと付き合っていたことが、脚本・シナリオにものすごく活かされていますよね。
――なるほど。当て書きが映画のクオリティを左右していたのですね。早川さんはいかがでしょうか?プロの目からご覧になられて。
早川 私自身が映画を撮る現場を知っているので、あぁ、わかる。あるあるみたいな感じで笑って観ていたんですけど、エンドロールにメイキング映像が出てきたときはもう胸が熱くなって。ぶわーって泣いちゃいました。映画を作ることへの情熱というか、熱量が一気にきて。照明が明るくなったときに、「なんでこの映画で泣いたの?」みたいな感じになっちゃって(笑)。

藤原 泣いたという人は結構いましたよ。俳優だったり映像の方だったり。
市橋 特殊メイクの人が時間のないなかゾンビメイクを仕上げていくところとか、実際のカメラマンが唯一休めるカメラを置いているタイミングで水を飲んでいるシーンとか。本当の撮影スタッフたちが映り込まないように隠れているところも。ちょっと泣けるんですよね。
――アジア、ヨーロッパ、南米など海外からの評価も非常に高いですね。
市橋 笑いというのは万国共通なのかもしれないですね。イタリアの映画祭で上映したときは「37分冒頭の42テイク目です」というセリフで笑った人が多くて。「ありえねぇ回数だろ!」と。それとかカメラを拭いた瞬間に血が付いたシーンでも爆笑していました。日本人の場合は、「ん? 何が起こったんだ!?」ってちょっと考えると思うんですけど、海外の人は「拭きやがったぜ!」みたいな感じで純粋に笑う。24時からの上映だったから、単に夜中のハイテンションだったのかもしれないけど。
早川 ほかの国でリメイクしたものを観たいくらいですよね。
藤原 リメイク版、観たいですね。国ごとに違いが出て面白そう。
市橋 まだこれからの話だと思うけど、可能性がなくはないということで(笑)。

わずか数百万円で作った作品が、シネコンで上映されるという奇跡
――いま、邦画の世界は好調といえるのでしょうか。TVドラマの拡大版や人気アニメの実写版は昔も今も観客が入っているイメージですが……。
早川 どうでしょうかね。でも、以前に比べていろんな作り方ができるようになっているのはポジティブなことだとは思いますね。クラウドファンディングもありますし、全体的にローコストで作れるというのもあって、作品自体の数も増えてきています。一般的には知られていないですけど、1週間のレイトショーに連日人がたくさん並んでいる作品も結構あるので、好きな方は映画館に足を運んでいるというのは感じますね。
市橋 意外と作品数が多いんだけど、長い期間上映するのが難しいんですよ。1ヶ月、それ以上となるとインディペンデントの場合はなかなか大変で。1週間から2週間というのが多いですね。
早川 しかも1日1回、レイトショーかモーニングショーか。
市橋 シネコンと違ってスクリーンの数が限られているミニシアターの場合、先々の細かいプログラムが決まっているわけです。ほかの劇場で上映するとか何かしらしないといけないけど、その交渉もなかなか難しい。限られた日数のなかで、どれくらいお客さんを呼べるかとか、話題を作れるかということを考えないと、たとえ評判が良くてもすぐに終わっちゃうんですよ。ただ、『カメラを止めるな!』と似たような流れで、『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』(中国で実際に起こったカンニング事件をモチーフに製作されたタイ映画)も“新宿のたった1館で始まった映画が日本全国で何10館”みたいな謳い文句でどんどん広がっています。だから純粋に面白い作品を作れたら、アプローチ次第でヒット作は生まれるんだなという兆しは感じていますね。数百万円で作った映画が、シネコンで上映されるなんて想像もしてなかったですから。
早川 しないですよね。奇跡的なこと。
藤原 前例のない話です。
市橋 シネコンに上映されること自体があり得ないと思っていたけど、今回のように劇場さんもそういう考えがあって、配給さんもそういうことをやってくれるんだなっていうのは驚きと同時に嬉しい発見でした。インディペンデントでがんばっている監督や役者さん制作の人たちが、「まだまだいけるじゃん!」みたいな前向きな雰囲気になっているから。
早川 そこは絶対に大きいです。こんなことが現実に起こり得るんだっていうのは。
藤原 それに映画だけに限った話ではないと思います。例えば演劇や何かを創作している人にとっても、お金があるからとか有名だからとではなく、良い作品ができればそんな可能性が見えてくるんだっていうのは、すごく大きな希望ですから。
■プロフィール

■プロフィール
早川千絵(左)
はやかわ・ちえ/NYの美術大学で写真を専攻しながら映像作品を独学で製作。帰国後の2012年に「ENBUゼミナール」に。卒業製作作品の短編映画『ナイアガラ』が、2014年カンヌ国際映画祭シネフォンダシオン部門、ソウル国際女性映画祭(グランプリ受賞)など、多数の映画祭に選出される。2018年には是枝裕和監督が総合監修を務めるオムニバス映画『十年 Ten Years Japan』の一編、『PLAN75』を監督。http://www.kujiraoffice.com
藤原佳奈(中)
ふじわら・かな/京都大学文学部を卒業後、2011年に「ENBUゼミナール」に。演劇創作ユニット<mizhen>主宰。演劇×動画の祭典、第5回クォータースターコンテストで『マルイチ』がグランプリを含む4賞を受賞。「日経COMEMO」(comemo.io)にてKOLとして連載を持つなど、ビジネス領域でも活躍。来年2月9日(土)から17日(日)まで、表参道のアパート「ビラ青山」で<mizhen>『渋谷区神宮前4丁目1の18』を公演。http://mizhen.info
市橋浩治(右)
いちはし・こうじ/1998年創立の「ENBUゼミナール」代表。資格スクールや大学・専門学校の生徒募集、広告営業を経て2009年より現職。ゼミの運営の傍ら、映画や舞台を鑑賞してはシーンの最前線で活躍する監督や演出家たちを講師として招聘。http://enbuzemi.co.jp
- Keywords: